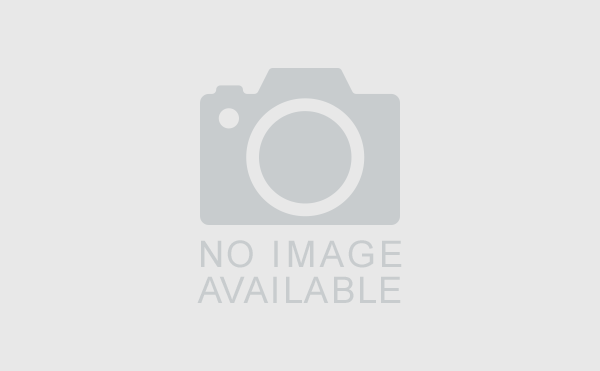見えると納得できる. !「お金のブロックパズル」で理解する利益と現金の関係
■ “わかっているつもり”の数字ほど危ない
前回の記事では、「利益」と「現金」は違うという話をしました。
でも実際の現場では、「なんとなくわかったけど、数字を見てもピンとこない」という声が多いんです。
その理由はシンプルで、頭では理解しても、イメージできていないから。
数字の話は“抽象的”になりがち。
だからこそ、経営者にも社員にも「見える化」することが大切です。
■ お金のブロックパズルとは?
私が経営支援の現場で使っているのが「お金のブロックパズル」。
会社のお金の流れを、積み木のような図で整理するツールです。
構造はとてもシンプル。
上から順にこう流れていきます。
売上
-変動費 = 粗利(付加価値)
-固定費 = 営業利益
-税金・返済・投資・社長の取り分 = 手元現金
この一連の流れをブロックで可視化すると、
「どこでお金が詰まっているのか」「どのブロックを動かせば改善するのか」が一目でわかります。
■ 家計にたとえるとこうなる
家計で考えてみましょう。
給料(売上)から、食費や光熱費(変動費)を引いて、残ったお金で家賃や通信費(固定費)を払う。
手元に残ったのが「黒字」です。
でも実際は、車のローン返済や子どもの教育費、住宅の修繕費などを払うと、通帳の残高は減っていきます。
家計でも、黒字=お金が増えるとは限りませんよね。
会社も同じ。
「利益が出ているのにお金がない」ときは、返済や投資など“見えない出費”に現金が流れているのです。
■ ブロックパズルを使うと何が変わるか?
経営数字を「ブロック」に置き換えると、社員にも伝わります。
たとえば、
「この固定費ブロックが少し大きいね。どうやったら小さくできる?」
「粗利ブロックを大きくするには、単価を上げるか、仕入を下げるしかないね。」
という具合に、数字が会話になる。
つまり、経営が“社長一人の悩み”から“チームの議論”に変わるんです。
数字がわかると、社員の行動も変わります。
「なんとなく節約」ではなく、「粗利率を1%上げよう」といった具体的な動きに変わります。
■ 「お金の流れを見える化する」ことが第一歩
利益と現金のズレを感覚でなく、構造で理解できるようになると、
経営判断にブレがなくなります。
「借入を減らすべきか」「投資すべきか」「人を採るべきか」——
すべての判断の根拠は“お金の流れ”の中にあります。
ブロックパズルは、その全体像を整理する“地図”のようなもの。
まずはこの地図を手に入れることが、キャッシュフロー経営の第一歩です。
■ まとめ
- 数字を「ブロック」で見ると、誰でも理解できる。
- 社員と経営者が“同じ地図”を見て話せるようになる。
- 見える化は、利益と現金の関係をつなぐ架け橋。
次回は、「お金のブロックパズル」でどうやってお金を“増やす”のか。
──粗利率・固定費・回転率の3つの打ち手について解説します。