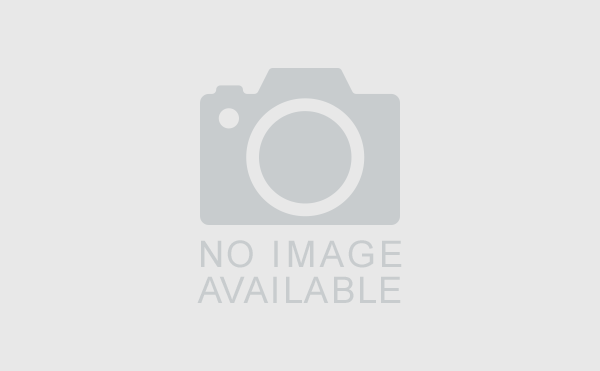「黒字なのにお金がない」その正体は?──利益と手元現金のズレを4つの視点で解説
■ はじめに:黒字倒産は「運」ではなく「構造」で起きる
「利益は出ているはずなのに、通帳の残高が減っている」
「決算は黒字なのに、資金繰りが苦しい」
こうした声を経営相談の現場でよく聞きます。
実はこれは珍しいことではありません。
なぜなら、「利益」と「手元現金」は似ているようで、まったく違うものだからです。
利益は“会計上の成績”であり、
現金は“今、会社に残っているお金”。
この2つの間には、いくつもの“時間差”と“性質の違い”が存在します。
それを理解しないまま経営判断をすると、
数字の上では順調なのに、現金が尽きる——いわゆる「黒字倒産」に陥ることがあります。
■ 利益と現金のズレが生まれる4つの典型パターン
では、具体的にどんなときに差が生まれるのか。
中小企業の現場でよく見られる4つのケースをご紹介します。
① 売掛金の入金が遅い
売上を計上した時点では、まだ現金は入っていません。
たとえば「3月に売上100万円、入金は5月」という取引なら、
3月決算では利益100万円が計上されても、実際にお金が入るのは2か月後。
その間に仕入や人件費、家賃を払えば、通帳残高は当然減ります。
BtoB取引が多い会社ほど、この“入金の遅れ”が資金繰りを圧迫します。
② 在庫が増えている
在庫は「将来の売上のタネ」ですが、
同時に「お金が商品に姿を変えた状態」でもあります。
例えば、現金100万円で仕入をした場合、帳簿上は資産が増えただけ。
利益には影響しませんが、手元のお金は確実に減っています。
在庫が積み上がるほど、現金は倉庫の中に眠ってしまうのです。
③ 借入金の返済
借入の返済額のうち、“元金”部分は経費になりません。
つまり、利益には影響しないのに、現金だけが銀行に出ていく構造です。
たとえば「毎月20万円返済×12か月=240万円」。
この金額は利益計算に含まれない“資金流出”。
黒字でも現金が減る要因のひとつです。
④ 設備投資・先行投資
新しい厨房機器や店舗改装、広告・採用など、
未来の売上を作るための投資も現金を大きく減らします。
会計上は「資産」として数年に分けて減価償却しますが、
現金は支払時に一気に減ります。
利益は安定していても、「今月の支払いが厳しい」と感じるのはこのせいです。
■ だからこそ、「利益」だけでなく「お金の動き」を見る
経営判断をするときに「今期はいくら利益が出たか」だけを見ても、
資金繰りの全体像はつかめません。
会社を“生き物”にたとえるなら、
利益は「筋肉の量」、現金は「血液の流れ」。
筋肉があっても、血が止まれば動けなくなります。
経営で大切なのは、「お金がどこで増え、どこで減っているか」を理解すること。
そのために有効なのが、キャッシュフロー経営です。
■ キャッシュフロー経営の第一歩:「お金のブロックパズル」
私のセミナーやコンサルティングでは、
会社のお金の流れを“見える化”するツールとして「お金のブロックパズル」を使っています。
これは、売上から経費・税金・借入返済・投資・社長の取り分までを、
ブロック図で視覚的に整理するもの。
どこにお金が詰まっているのか、どこを改善すべきかがひと目でわかります。
利益と現金の関係を理解すれば、
「通帳の数字に振り回される経営」から脱却できます。
黒字倒産を防ぐ第一歩は、「お金の流れを意識して見る」ことなのです。
■ まとめ
- 利益は“成績”、現金は“実際の体力”。
- 売掛金・在庫・返済・投資がズレを生む。
- キャッシュフローを意識すれば、経営は安定する。
次回のブログでは、この「お金のブロックパズル」を使って、
あなたの会社のお金の流れをどう整理するかを解説します。