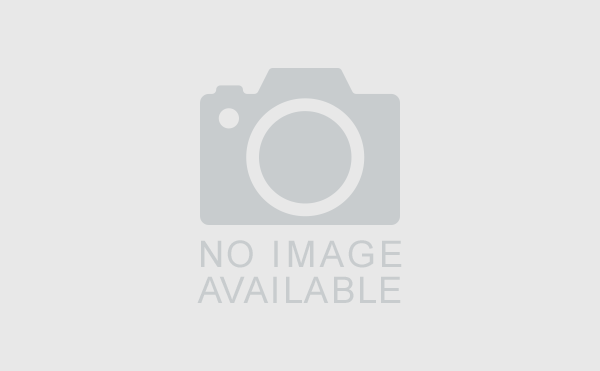最低賃金1,500円時代のインパクト
〜“数字で備える”経営へ〜
2025年度の最低賃金は全国平均 1,121円(+70円) となりました。
政府は「全国平均1,500円」を目標に掲げています。
つまり、あと379円、約34%の上昇が見込まれています。
最低賃金が上がるということは、単に「給与が増える」だけではありません。
中小企業にとっては、経営の根幹である利益構造そのものを見直すきっかけになります。
年400万円規模のコスト増も
たとえば、時給制スタッフ5名が
1日8時間×月22日働いているとします。
- 現在:1,121円 × 176時間 × 5人 = 月98.7万円
- 1,500円時代:1,500円 × 176時間 × 5人 = 月132万円
差額は 月33万円、年間約400万円の人件費アップ。
もし粗利が月360万円(売上600万円・粗利率60%)なら、
人件費が33万円増えると 粗利の約9%が消える 計算になります。
利益率5%の会社であれば、黒字が一気に赤字に転落しかねません。
鍵は「粗利で考える」
こうした波を乗り越えるためには、「売上を増やす」よりも、
“粗利で考える”発想が欠かせません。
粗利とは、売上 − 変動費(仕入・材料費など) のこと。
固定費である人件費を支えるのは、この粗利しかありません。
つまり、最低賃金の上昇分を補うには、
「粗利をどう増やすか」を戦略的に考える必要があります。
- 単価・客単価の見直し
少しの値上げでも、全体では大きな効果になります。 - 人時生産性(1人が1時間で生み出す粗利)を高める
1時間で5,000円の粗利を生んでいた仕事を、6,000円にできれば、
人件費が上がっても十分に吸収できます。 - 業務の分担やシフト配置の見直し
人の重複をなくし、ピーク時間帯に集中させることで、
同じ人員でも成果を上げられます。 - 仕組みやツールの導入による効率化
ITや自動化ツールを活用して、1人あたりの生産性を引き上げる。
こうした小さな改善の積み重ねが、結果として数百万円規模の効果を生みます。
数字を“見える化”してチームで共有する
最低賃金1,500円時代に求められるのは、
「感覚経営」から「数字経営」への転換です。
お金のブロックパズルを使えば、
- 人件費が何%上がると利益はいくら減るのか
- 損益分岐点売上はいくらになるのか
- どれだけの粗利を確保すれば会社が守れるのか
が一目でわかります。
これを社員と共有することで、
経営者だけでなく**チーム全体が“利益をつくる意識”**を持てるようになります。
ピンチをチャンスに変える
最低賃金1,500円時代は、避けられない未来です。
しかし、それは「経営の危機」ではなく、
会社の仕組みと人の働き方を見直すチャンスでもあります。
人件費を「負担」ではなく「投資」として捉え、
粗利を生み出す構造を整えること。
そして、数字で語れる経営へシフトすること。
これが、これからの時代を生き抜く企業の共通点になるでしょう。