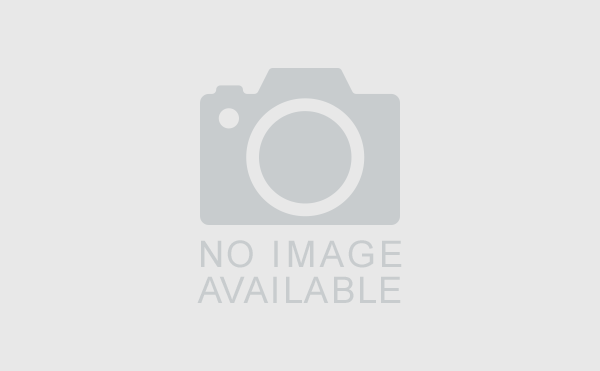最低賃金上昇はピンチかチャンスか?
<中小企業が取るべき3つの視点>
2025年10月1日より最低賃金が引き上げられます(全国平均63円)。
最近は毎年のように上昇しています。
「また人件費が上がった…」と頭を抱える経営者も多いのではないでしょうか。
例えば、時給が50円上がるとします。
アルバイトスタッフ1人が1日8時間、月20日働くと、月8,000円のコスト増。
5人いれば月4万円、年間で約50万円。
中小企業にとっては決して小さな金額ではありません。
しかし、この「最低賃金上昇」をただのコスト増と捉えるか、未来へのチャンスと捉えるかで、その後の経営は大きく変わっていきます。
今回は、経営者が押さえておきたい 3つの視点 をご紹介します。
1. 人件費は「経費」ではなく「投資」
多くの経営者が「人件費=固定費の負担」と感じています。
確かに、利益を圧迫する要因になるのは事実です。
ただし、人件費は社員やスタッフが働き、価値を生み出すために必要な「投資」でもあります。
最低賃金の上昇は、スタッフにとって「より良い労働環境」や「働きがい」を提供するきっかけにもなります。
「お金がかかるから人を減らす」のではなく、人を活かして売上や粗利を伸ばすための工夫を考えることが大切です。
例えば、接客業なら「お客様との会話を増やすことで、リピート率を高める」。
製造業なら「多能工化を進めて、一人あたりの生産性を上げる」。
人件費を“投資”としてどう活かすか?
この問いが経営者に求められています。
2. 粗利で考える
最低賃金上昇の影響は、最終的には「粗利」と「固定費」のバランスに現れます。
売上が増えなくても人件費が増える。
その分、利益率が下がり、利益が圧迫される。
これは飲食業や小売業など、価格転嫁が難しい業種ほど深刻です。
だからこそ大切なのは、「粗利をどう確保するか?」という発想です。
- 値上げによる価格転嫁(小さな単価改定でも積み上がる)
- メニューや商品の付加価値を高めて客単価を上げる
- 在庫ロスや仕入れの無駄を減らして粗利を守る
「売上を増やす」だけでなく「粗利を守る・高める」という発想が重要です。
3. 経営数字で「見える化」する
最低賃金上昇の影響は、感覚だけで判断すると誤りやすいものです。
だからこそ「数字でシミュレーションする」ことが必要です。
例えば、「お金のブロックパズル」という図解を使うと、
- 人件費が増えたら、どれだけ売上が必要か
- 利益がどれくらい減るのか
- 赤字にならないための損益分岐点はどこか
が一目で分かります。
社員と共有して「来年は人件費が○万円増える。だから売上をこれだけ増やそう」と話し合えば、経営者だけが悩むのではなく、チームで危機感と目標を共有できるようになります。
数字で“見える化”することは、経営者の孤独を減らすことにもつながります。
まとめ:守りと攻めを同時に考える
最低賃金上昇は避けられない流れです。
「守り」として経費削減を考えるのも大切ですが、それだけでは未来は開けません。
むしろ、「攻め」として 付加価値を高め、粗利を改善する取り組みを同時に進めることが、これからの時代の経営には欠かせません。
- 人件費は「投資」として活かす
- 粗利で考え、利益を守る
- 経営数字でシミュレーションし、社員と共有する
この3つを押さえておくことで、最低賃金上昇を「ピンチ」ではなく「チャンス」に変えることができます。
おわりに(行動のきっかけ)
もし今、「最低賃金が上がったらウチは耐えられるのか?」と不安を感じている方は、ぜひ一度、自社のお金の流れをブロックパズルで整理してみてください。
来週のセミナーでは、実際の事例を交えて「最低賃金上昇への備え方」をお伝えします。
数字で未来を見える化し、一緒に考えてみませんか?